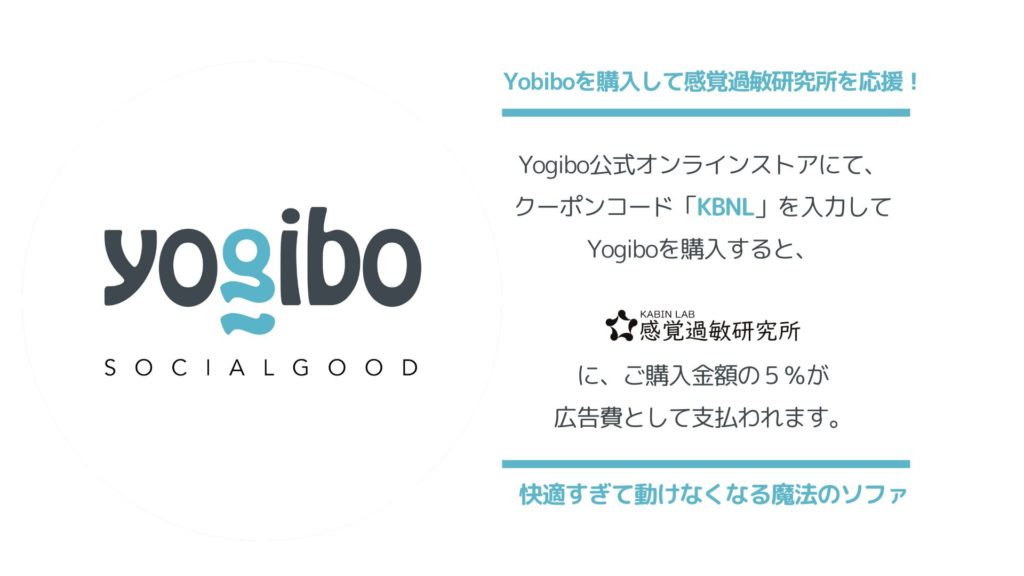感覚過敏研究所ライターの「うち」です。私には嗅覚過敏があります。
比較的症状は軽く、生活に支障があるほどではない。が、日常生活の中で不快や苦痛を感じることは多々ある。特に列車内では不快な思いをすることが多い。閉鎖的な空間故に、様々なニオイが充満するからだろう。
シートのクリーニング液、エアコンなど、列車内でのニオイはいろいろとあるが、今回は「人のニオイ」のエピソードをお伝えしたい。「人のニオイ」というと、汗臭さや加齢臭が思い浮かぶかもしれないが、それらではない。題名にある通り、高校生カップルのニオイの話だ。
嗅覚過敏と田舎の列車事情
一応、お断りをしておくと、私が利用しているのはローカル線で、実際に乗っているのは「列車」ではない場合がある。車両が少ないときは1両だからだ。高校のテスト期間中で部活動が無いと、日曜の朝には貸し切りのことすらある。
ここまで読んで、とんでもない田舎を想像した方は多いだろう。おそらく、想像通りの田舎ではあるが、ビックリするくらいに列車内が混むこともある。貸し切り状態になるのは、「地元を通るローカル線」「高校のテスト期間中」「日曜の朝」という条件が揃ったときだ。もちろん、毎回貸し切り状態になるわけではない。
いくら田舎県とはいえ、本線は度々混む。本数が少ないため、巡り合わせが悪いと驚くくらい混むこともある。もちろん、ラッシュ時とは比べものにならないが、都会で昼間に乗る列車と特別に変わらない。
時に貸し切り状態で嗅覚過敏に優しいが、都会と変わらないほどの混み具合を見せることもある。それが田舎の列車事情だ。

嗅覚過敏と列車内の過ごし方
列車内がすいているとき、私はできるだけ座るようにしている。座っていると、いくらかは人と離れることができるからだ。これも田舎ならではだと思うが、座席にある程度の空きがあっても、乗客は座る素振りを見せず立っている。少なくとも、身体が触れるような座り方はしない。
その日は日曜日だったため、列車内は比較的すいていた。本線に乗り換えても座ることができた私は、いつものようにスマホの画面に集中した。人の顔と離れることで、化粧品、整髪料、シャンプーなど、様々なニオイから少しでも離れていると思えるからだ。さらに、両隣に座っている人とも離れようと、少し大げさなくらいにスマホの画面を覗き込んだ。
普段、苦手なニオイがしても、あからさまな行動をなるべくしないように心がけているが、こうして文字に表してみると、私の不自然な動きに不快感をもつ人もいるのではと思えてくる。ひょっとすると、不審者扱いされるかもしれない。そうならないためにも、様々なニオイの中、列車内では、できる限りの我慢をしている。ただ、我慢にも限界がある。
嗅覚過敏と高校生カップルのニオイ
「ああ、近付いてくる」と思ったときにはもう遅かった。息を止めたくなる程のニオイが目の前で止まった。正確に言うと、ニオイを感じたときに息を止めてやり過ごそうとしたのだが、運悪く目の前で止まられてしまった。再び息を吸ったとき、強烈なニオイが鼻の奥まで進入してきた。
あまりのニオイに吐き気を催し、思わず少し顔を上げると、目の前につないだ手が見えた。おそらく高校生だろう。だが、今さら席を立つのはあまりにも不自然だ。あと一駅、5分程で目的地に着く。私はなんとか我慢を続けることを選び、再びスマホに集中・・・
できるわけがなかった。

強烈なニオイは男性用の香水だった。女性用のニオイも混ざっていたような気もするが、強烈すぎてよく分からなかった。とにかく、男性用の香水が、ものすごいニオイを発していた。手首につけるという話は聞いたことがあるが、その時の彼は、全身からニオイが漂っているように思えた。
後ほど調べてみると、香水はウエストや太ももの内側、ヒザの内側、足首にもつけるらしい。頭や脇につけてしまうと、体臭と混ざったニオイが立ち上るそうだ。彼も、おそらく全身に香水をつけていたのだろう。
もしかすると、休日のデートは初めてかもしれない。ちょっと張り切りすぎて、多めにつけてしまったのかもしれない。もちろん、彼に悪気はない。そんなことを自分に言い聞かせ、スマホの画面を見ていたが、限界だった。
再び顔を上げた。今度は2人の顔が見える位に。彼は彼女に寄り添い、彼女のスマホを覗き込んでいた。彼女は右手をつなぎ、左手でスマホを持ち、彼に見せていた。
そして、左手をいっぱいに伸ばした彼女の上半身は、彼から逃げるようにのけぞり、顔は軽く背けられていた・・・
もしかすると、彼女も嗅覚過敏かもしれない。嗅覚過敏でなくても、彼から離れたくなるほどのニオイだったかもしれない。私はなぜか、彼から逃げてはいけない気分になり、再びスマホの画面に目を落とした。
程なくして目的地に着くと、2人は先に降りていった。駐輪場に向かうとき、男の子を後ろから追いかけて、手をつないだ女の子がいた。さっきの2人だった。彼女から手をつないだ様子を見て、私は少しだけ安心した。本当に余計なお世話でしかないが、彼が適量の香水をつけることができるようにと切に願った。
※鮮明に思い出すと気持ちが悪くなるため、また、個人が特定されないため、ある程度フィクションとなっています。